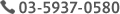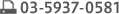公開日 2024年10月13日
首相が代わっても「円安」は終わらない、縮小された経済政策をせざるを得ない「ポスト石破」に待ち受ける
「金利ある世界」で求められる難しい舵取り
9月27日の自民党総裁選挙を経て石破茂氏が第28代総裁に選出され、10月1日の第214回臨時国会において第102代首相に指名された。石破首相の経済政策観については様々な情報が交錯しているものの、今は考えても詮無きことであろう。
既報の通り、石破氏は10月9日に衆議院を解散し、10月27日に投開票を行う方針を表明している。発足直後で新政権に新鮮味があること、野党の一致協力が進まないうちに勝負をつけたいことなどが決断の主たる動機だろう。
総選挙前に本音の話ができるはずもない。補正予算編成などを通じて「石破カラー」が出されていくとすれば、それは総選挙後の話になるだろう。
「金利のある世界」でバラマキ政策は通用しない
もっとも、誰が日本経済の指揮を執るにせよ、今後の日本が人口減少を背景として名目賃金の上昇が持続性を伴い「デフレからインフレへ」という大きな経済環境の変化に直面することはほぼ既定路線である。
それは言い換えれば「金利の無い世界」から「金利のある世界」への局面変化をも意味する。
四半世紀以上も変わらなかった財政・金融政策の大前提が変わる中、新政権の経済政策は執行されなければならない。その大前提の変化は何を意味するのか。
一般論に倣えば、「金利のある世界」での歳出は「金利の無い世界」でのそれに比べて抑制的であることを求められ、いわゆるバラマキと揶揄される拡張財政路線は望む・望まないにかかわらずやりづらくなる。
しかし、それが嫌だからと言って「金利の無い世界」を志向すれば、今度は円安がぶり返す。
結局、石破首相(やそれ以降の政権与党)は「円安か金利上昇の二者択一」を迫られる中、今までよりも制限された経済政策(財政・金融政策)の手札で執政が求められる。
これまでのように何かにつけて低所得世帯に財政出動を頻発するような財政運営を重ねていれば、為政者の制御が働きにくい為替市場において野放図な通貨安のリスクが高まるだけである。
必然、選択できる経済政策の組み合わせは過去の政権よりも限定的になる。
データが示す「円から外貨」の流れ
こうした政治環境の中、9月19日に日銀から公表された今年4~6月期の資金循環統計が教えてくれる情報は非常に重要であるように感じられた。
結論から言えば、今回の結果は本邦家計部門における「貯蓄から投資」の動きを再確認するものであり、それ は「円から外貨」を意味する動きでもあった。
日米金利差縮小にもかかわらず、意外と底堅い推移を示すドル/円相場を理解する上でも、やはり注視したい計数である。

では数字を見てみよう。今年6月末時点で家計部門の金融資産は前年比+4.6%増加の2211.7兆円と6四半期連続で過去最高を更新している。
記憶に新しいように、円安・株高がピークを迎えたのが7月上旬であるため、こうした仕上がりは想像できたものだ。
毎回注目している筆者試算の外貨性資産は101.7兆円と初めて100兆円を突破し、総資産に占める割合は4.6%とやはり過去最高であった。
2000年3月末と比較すると金額にして約7.7倍、比率にして約5倍まで膨らんでいる。「貯蓄から投資」は徐々に、しかし確実に「円から外貨」という形態で進んでいる。
また、株式・出資金も初の300兆円台に乗せ、比率も13.6%とやはり過去最高水準であった(厳密には3月末の13.7%が過去最高)。
2000年3月末と比較すると金額にして約2.2倍、比率にして約1.4倍まで膨らんでいる。少なくとも今年上半期に関しては、日本の家計部門は資産運用立国の旗印の下、投資意欲を遺憾なく発揮しているように見える。
「家計の円売り」が円安の底流に
もちろん、8月上旬の相場変動が反映される次回9月末時点の数字はまた異なった姿になるはずだ。
とはいえ、8月以降も家計部門の投資意欲がさほど衰えていないことは月次で確認される投資家部門別の対外証券投資からも確認済みである(8月の投資信託経由の対外証券投資は+1兆1702億円で過去3番目に大きな買い越しであった)。
9月末時点の資金循環統計では、円高の影響もあって外貨性資産比率が低下する可能性はあるものの、それをもって「家計の円売り」が退潮になったと判断はできない。
ちなみに近年急増が指摘される外貨建て生命保険は統計の制約上、保険・年金準備金に含まれている。これが金額にして544.7兆円、比率にして24.6%と非常に大きい。
通貨建ての内訳を知ることは叶わないが、もし保険・年金準備金のわずか1割でも外貨建て資産だと仮定した場合、外貨性資産の比率は7%を超えるし、2割だとすれば10%に肉薄する。保守的に考えるのであれば、実態として日本の家計金融資産の10%近くがすでに外貨建てになっている疑いは持っても良い。
外貨建て資産を資産別に見た場合、やはり全体をけん引しているのは投資信託で、筆者試算では金融資産全体に対し2.6%が投資信託である。
これに対外証券投資(1.7%)、外貨預金(0.3%)が続いているが、上述したような外貨建ての保険商品が仮に保険・年金準備金の1割だと仮定すると対外証券投資を超え、投資信託に匹敵する存在感を放つことになる。
繰り返しになるが、統計で捕捉できる以上に日本の家計部門における「円から外貨」は進んでおり、これが円安相場の底流にある可能性は否めない。
「金利上昇」よりも「円安」が許容されやすいワケ
冒頭にも言及したように、今後の日本経済は誰が指揮を執ることになったとしても、円安か金利上昇か、いずれかを受け入れる必要がある。
結局、円安やこれに伴う株高を放置した場合のスナップショットが今年3月末や6月末の資金循環統計であり、数字だけを見れば前向きなイメージが得られる。
9月以降の同統計は「金利上昇を前提とした場合、家計金融資産が目減りする」という絵図が示される可能性がある。それ自体、政治的には愉快な話ではないだろう。
また、金利上昇それ自体は住宅ローン金利上昇などを念頭にやはり政治的に嫌気されやすい論点ではある。
実質所得環境の悪化を促す円安も決して甘受できる相場現象ではないが、短い時間軸で「政治的な失点に繋がりやすい」という意味では金利上昇は政治的に受け入れ難いという胸中は察するに余りある。
こうした認識に立つと、為政者として金利上昇と円安の二者択一を迫られた場合、望む・望まないにかかわらず、やはり円安が選択されやすいかもしれない。
マクロ経済政策の組み合わせ(ポリシーミックス)で考えると、財政政策は金利上昇リスクに配慮して緊縮寄りにするものの、通貨・金融政策は円安・緩和寄りという選択である。
もっとも日本において前者が選択されるのかどうかは多分に怪しいものがあるため、結局、野放図なマクロ経済政策運営の下、国債市場はともかく為替市場が円売りで攻め込まれる状況は出現しやすい。
とはいえ、この期に及んでは「二者択一で済めば良い」という心構えも必要だろう。
今後、日銀の連続利上げが行われる未来がもし到来するのならば、それは通貨防衛の手段として執行されている可能性が高く、その時点では円安と金利上昇が同時発生している可能性が高いと筆者は懸念している。
言い換えれば、いわゆる「金利のある世界」が定着する状況を想定した場合、恐らくそうすることでしか円安を抑制できないという差し迫った状況に陥っているのだと推測する。
避けたい日本版トラスショック
とりあえず石破首相は通貨・金融政策に対してタカ派(引き締め)の姿勢で知られているため、上記のような懸念が大きいとは言えない。
確かに、10月2日、植田総裁と会談した石破首相が「個人的には現在、追加の利上げをするような環境にあるとは考えていない」と述べたことが本稿執筆時点では話題となっている。一方で「金利についてとやかく申し上げることではない」とも述べており、どこまで思想性が強い発言なのかは正直、まだ図りかねる部分がある。
その意味で今次政権においては差し迫った脅威を覚える市場参加者は多くないように思う。
しかし、今回の総裁選において高市氏が接戦を演じたことの意味は侮れない。
仮に石破政権の運営が早期頓挫してしまった場合、再び金利引き下げや財政出動によるリフレ政策への期待が浮上してくる可能性はある。
第二次安倍政権があれほどリフレ思想に染まった背景には2000年8月の出来事がある。ゼロ金利政策解除の決定に際し、日銀が政府の議決延期請求権を否決し、政府と日銀の溝が深まった。この時の怨恨が強く作用したという説がもっぱら持ち出される。当時、官房副長官だったのが安倍氏であった。
まとめると
財政・金融政策にタカ派的な石破氏が失敗した場合、必然的に「では対照的な思想の持ち主に…」という発想に発展する可能性は十分ありうる。
しかし、今後の日本において政府が日銀の政策運営、具体的には利上げを露骨にけん制した場合、ほぼ間違いなく為替市場が円安という形でその負荷を引き受けることになる。
その円安が日本社会に多大な痛みを強いる場合、「やはりある程度の金利上昇は必要」というムードは盛り上がらざるを得ない。世論が傾けば、政府的にも利上げの容認は進まざるを得ない。
結果、円安と金利上昇が併発する恐れはある。この状況を世論が前向きに評価することはないだろう。結局、中央銀行の政策運営を無為に束縛すれば、政権の持続性に関わる。
過去2年半の円安相場は歴史的相場であり、ピークこそ一旦過ぎ去っているものの、日本の金利・為替市場は非常にデリケートな状況にあることを為政者には認識してもらいたいと願う。
◇