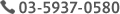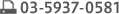公開日 2024年11月23日
「現役世代にカネを返せ」、
高齢者相手の新聞やテレビが報じない、「103万円の壁」撤廃の本当の意味
調べてみました、
◇
『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』などマネー関連書籍のベストセラー作家、橘玲氏が話題の時事ネタを独自の視点で考察する。
「103万円の壁」を因数分解する
「壁」問題を理解するためには、「103万円の壁」は所得税(および住民税)の問題で、「106万円の壁」「130万円の壁」は第3号被保険者制度と社会保険制度の問題であることを分けて考えなくてはならない。
メディアは「103万円」の根拠を、「48万円の基礎控除と55万円の給与所得控除の合計」と説明している。しかしこれでは、なんのことなのかわからないひともいるだろう。
第1のポイントは、「収入(年収)」と「所得」のちがいだ。収入というのは会社でいう売上で、所得は経費を引いたあとの純利益になる。法人では純利益に対して法人税が課せられるように、個人では所得に対して所得税を納める。
個人で飲食店を経営している自営業者を考えるとわかりやすいが、売上(収入)が500万円だとしても、食材の仕入れや店舗の家賃、アルバイトの人件費、銀行からの借入に対する利子など、さまざまな費用が必要になるだろう。その経費の合計が300万円だとすると、500万円の売上から300万円を引いた200万円が純利益だ。
基礎控除というのは、「生きていくのに必要最低限の所得には課税しない」ということで、日本では48万円になっている。そこで200万円の所得(純利益)から48万円の基礎控除を引いた152万円がこの自営業者の課税所得になる。
給与所得控除は「サラリーマンの必要経費」
では、給与所得控除とはなんだろうか。これは、サラリーマンの必要経費を国が便宜的に決めたものだ。
交通費や会議費、出張費など、日々の仕事にかかる経費の大半は会社が払ってくれるだろうが、それでもパソコン代やスマホの通信費、背広代、勉強のための資料代など、会社に請求できない出費があるだろう。
しかしこれを、会社員一人ひとりが確定申告の際に個別に提出すると、税務署の仕事がパンクしてしまうので、会社の経理部が代わりに所得を計算して年末調整で処理できるようにしているのだ(日本では、税務署が税額計算と徴税の仕事をタダで会社にアウトソースしている)。
給与所得控除(サラリーマンの経費)は給与収入によって決まっていて、年収162万5000円以下は一律55万円、年収850万円超は一律195万円などとなっている。
基礎控除(48万円)と給与所得控除の最低額(55万円)を加えた103万円というのは、サラリーマンとして生きていくのに最低限必要なお金で、年収がこれ以下の場合は(生きていけなくなるのだから)課税しないという理屈になる。
ここまでの説明で、「ほとんどの経費は会社に請求しているから、年55万円も仕事のための自腹を切ってない」と思ったひともいるだろう。
これはもっともで、「給与所得控除が過大だ」というのはずっと指摘されてきたが、「自営業者だって適当に経費を水増ししているから、会社員にだけきびしくするのは不公平だ」ということで、この「寛大な」金額になっているらしい。
「月4万円」では生活できない
「103万円の壁」は、「所得税が課せられるのを避けようとして、パートや学生のアルバイトがこの金額を超えないようにしている」ことからつけられたが、配偶者特別控除などの救済制度があるので、実態としてそのような就業調整は起きていないという「103万円は幻の壁」説もある。
こうした批判はもっともだが、ここでは「103万円はほんとうの壁か」というあまり意味のない話は脇に置いておいて、基礎控除について考えてみよう。
なぜなら、国民民主党の主張は(はっきりいっているわけではないようだが)「48万円の基礎控除を75万円引き上げて123万円にする」というものだからだ。メディアはこれを、「103万円の壁が(75万円増えて)178万円になる」と報じるが、これだと議論の本質がわからなくなってしまう。
まず押さえておくべきは、基礎控除の本来の意味が「生活に必要な最低限の所得」だということだ。このように理解すれば、誰だって現在の48万円という金額がバカげていると気づくだろう。
月額4万円で生きていけるわけがないのだから、「荒唐無稽な基礎控除を、現状に合わせて123万円(月額約10万円)にする」という政策には相応の合理性がある。
必要なのは、現役世代の減税
では次に、基礎控除を引き上げるとなにが起きるか見てみよう。
日本の所得税は累進課税で、所得の少ないひとは税率が低く、所得が多くなるほど税率が高くなっていく。
課税は1000円単位なので、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた課税所得が1000円を超えると5%の所得税が課せられる。
税率は10%、20%、23%、33%、40%と所得に応じて上がっていき、年収4000万円以上で上限の45%になる(年収が上がるにつれて所得税の控除額も増え、税率45%では479万6000円が収入から差し引かれる)。

出典:国税庁
個人の所得には所得税に加えて住民税も課せられる。所得税(国税)と住民税(地方税)は所得の計算方法にちがいがあるが、東京都の場合、都民税(4%)と区市町村民税(6%)を合わせた10%の所得割に、所得の有無にかかわらず1人あたり4000円(都民税1000円+区市町村民税3000円)の均等割がかかる。
年収には個人差があるが、現役世代のボリュームゾーンは所得税率が10%か20%だろう。これに住民税の10%を加えると、現役世代の多くが所得の20%(所得税10%+住民税10%)から30%(所得税20%+住民税10%)の税を納めていることになる。
国民民主党が提案するように、基礎控除を75万円引き上げて、それが所得税と住民税に適用されるとすると、なにが起きるだろうか。この計算は簡単で、減税額は75万円にそれぞれの個人の税率を掛ければいい。
所得税と住民税を合わせて20%の税を納めているひとは、基礎控除の引き上げによって、手取りが年に15万円(75万円×20%)増える。所得税・住民税の合計が30%なら、手取りは22万5000円(75万円×30%)増えることになる。
すなわち、「基礎控除の引き上げは所得のある現役世代への大規模な減税」なのだ。このポイントを押さえないと、国民民主党がネットやSNSで若者・現役世代からなぜ強い支持を得ているのかが理解できない。
今こそ、不平等と歪みの見直しを
これを逆にいうと、基礎控除を引き上げても、そもそも所得のないひとには何の意味もないということだ。
その典型が年金受給者で、基礎控除の48万円に年金控除の110万円を加えた年158万円が所得から差し引かれる。65歳以上は収入に応じて国民健康保険料がかかり、75歳以上は年約5万円の後期高齢者医療制度の保険料が生じるが、これらも所得から控除される。
それに対して、国民年金の平均受給額は月額5万5000円、厚生年金で月額14万6000円ほどだから、受給者の6割から7割ちかくはもともと所得税を払っておらず、基礎控除額引き上げの恩恵を被れない。
年金に生活を依存する高齢者の多くは、自分たちにメリットのない減税に関心がないだけでなく、大規模減税によって社会保障制度が揺らぐことを不安に思うだろう。これが(おそらく)、高齢者を読者・視聴者にしている新聞やテレビが「103万円の壁撤廃」に否定的な理由だ。
人類史上未曽有の少子高齢化が進む日本ではこれまで、現役世代から「搾取」して高齢世代に「仕送り」をするのが当たり前だった。いまの若者たちは、「高齢者に押しつぶされる」という強い不安を抱えている。
だがこの不平等を指摘すると、「リベラル」を名乗るメディアや識者から「世代間対立を煽る」と批判・罵倒されてしまう。
国民民主党の「手取りを増やす」という政策は、この「壁」を破って世代間の不平等や税・社会保障制度の歪みを政治の俎上に載せたことに大きな意義がある。
◇まとめ
「103万円の壁」撤廃が基礎控除の引き上げによる(所得のある)現役世代への大規模な減税であることを説明したい。
そもそも打ち出の小槌のように空からお金が降ってくるわけではないのだから、7兆円を超える大規模な減税が日本社会になんの影響ももたらさないなどということはあり得ない。
国民民主党は、「基礎控除の引き上げによって(所得のある)現役世代にお金を返すのと、ごく一部の既得権層にわけのわからない補助金をばら撒くのと、どちらを選ぶのか」を正面から国民に問うべきだろう。