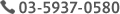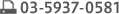公開日 2025年02月09日
こんにちは
今年、2025年にも、さまざまな不動産にかかわる法改正が実施済み、または予定されています。
今回は、宅建業法ならびに建築基準法における改正点を解説します。
宅建業法の改正
宅建業法の中では、11の改正点を解説します。
いずれも覚えておきたい事項ではありますが、特に、(5)と(9)と(11)は最重要ポイントになります。ぜひチェックしてください。
(1)宅建業の免許申請書の改正
(2)宅建業者名簿の記載事項の改正
(3)宅地建物取引業者名簿等の閲覧
(4)従業者名簿の記載事項
(5)事務所に設置する標識の記載事項
(6)都道府県知事への免許等に関する情報の提供
(7)専任と取引士の専任性
(8)欠格事由に該当することとなった場合における届出
(9)レインズの機能強化
(10)報酬額の掲示
(11)低廉な空き家等の報酬額の計算
昨日に続き、どのような内容なのか見ていきましょう。
(9)レインズの機能強化【重要】
2025年1月より、売主が自らの物件の取引状況を確実かつ簡単に確認できるよう、宅建業者に対して、レインズへの物件の取引状況の登録を義務付けるとともに、宅建業者から売主に交付される登録証明書に2次元コードを掲載し、売主専用画面へのアクセスを向上させるという改正が行われました(宅建業法34条の2)。
なお、レインズ(REINS)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産取引の情報ネットワークシステムです。宅建業法に基づき、登録された物件情報は宅建業者間で共有される仕組みです。
この改正は、不動産仲介による物件のいわゆる「囲い込み」防止がその趣旨です。
不動産仲介の囲い込みとは、たとえば、売主も買主も自社から仲介するために、レインズに「売主都合で一時紹介停止中」などと虚偽の登録をし、他の業者に紹介させないといった行為をいいます。
試験対策的には条文も確認しておくとよいでしょう。太字の部分が追加されました。

さらに、ガイドラインにも重要な変更・追加がありますので、一部引用します。
太字の部分が変更部分・追加部分です。特に、9(2)の通知については、旧規定では「通知に努めること」でしたが、それが「通知すること」になった点と、違反した場合に監督処分になる旨が明記された点が重要です。
第34条の2関係
1 依頼者への周知について
(4) 宅地建物取引業者が依頼物件を指定流通機構に登録した場合は、当該宅地建物取引業者から指定流通機構が発行する登録済証(以下「登録証明書」という。)の交付を受けることにより登録されたことを確認するとともに、レインズ(指定流通機構が運営する宅地建物取引業者間の物件情報交換システムをいう。以下同じ。)のステータス管理機能を通じて当該依頼物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の最新の登録内容を確認すること。
9 指定流通機構への登録等について
(1)登録証明書の交付時における説明等について
宅地建物取引業者は、指定流通機構に物件を登録したときは、登録証明書を交付する際に、レインズのステータス管理機能を通じて当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の最新の登録内容が確認できることに関し、依頼者に対して分かりやすく説明を行うことが望ましい。なお、宅地建物取引業者が専属専任媒介契約及び専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した物件について、当該物件に係る取引の申込みの受付に関する状況等の登録内容が事実と異なるときは、法第65条第1項の指示処分の対象となる。
(2)成約情報の通知について
宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約又は専任媒介契約に基づき指定流通機構に登録した物件について契約が成立したときは、法第34条の2第7項及び規則第15条の13の規定により、当該指定流通機構に取引価格を含む成約情報を通知しなければならないこととされているところ、成約情報は、媒介価額の評価を行う際の参考として宅地建物取引業者に提供され、さらに指定流通機構が公表している平均取引価格等の市況情報の基になるものであり、不動産流通の円滑化に極めて重要な役割を果たしている。
宅地建物取引業者は、こうした成約情報の通知の重要性や、通知を怠った場合には法第34条の2第7項に違反することとなるという点を十分に認識し、通知義務の履行を徹底すること。 また、一般媒介契約の場合も、指定流通機構に登録した物件については、契約が成立した場合において、当該指定流通機構の定める規程等に従い、成約情報を通知すること。
(10)報酬額の掲示
宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません(宅建業法46条4項)。
これに関するガイドラインについて、以下が追加されました。これは標識と同じ趣旨の改正です。
第46条第4項関係
デジタルサイネージを活用した報酬の額の掲示について
書面ではなく、デジタルサイネージ等ICT機器を活用した掲示についても、以下の要件を満たす場合には、書面による掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第46条第4項の規定による報酬の額の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。
(1) 宅地建物取引業者の営業時間内その他の公衆が必要なときに報酬の額を確認できるものであること。
(2) 当該デジタルサイネージ等において報酬の額を確認することができる旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること(画面の内外は問わない。)。
(11)低廉な空き家等の報酬額の計算【重要】
空き家などの報酬額の計算方法が変わりました。
ポイントは、
・物件価格の上限が400万円から800万円になったこと
・売主だけでなく買主からも現地調査費用等を受領できるようになったこと
・通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するという要件が削除されたこと
・現地調査費用は実費に限定されなくなったこと
・代理の場合は現地調査費用も含めて2倍できるようになったこと
・空家等の貸借の仲介については通常の2倍の報酬を得られること
となります。
以下、私の著書(「2025年度版これで合格宅建士上巻」)から実際の計算方法を引用します。
(1)低廉な空家等の売買・交換の媒介における特例
宅建業者は、低廉な空き家等の売買または交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(媒介に係る消費税等相当額を含む)について、媒介に要する費用を勘案して、前記の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができます。
低廉な空き家等…売買に係る代金の額(その売買に係る消費税等相当額を含まない)または交換に係る宅地・建物の価額(その交換に係る消費税等相当額を含まない。また、交換に係る宅地・建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額をいう)が800万円以下の金額の宅地・建物をいいます。なお、その宅地・建物の使用の状態を問いません。
「媒介に要する費用」は人件費等を含みます。また、「費用を勘案して」とは、報酬額の算出に当たって、取引の態様や難易度等に応じて媒介業務に要すると見込まれる費用の水準や多寡を考慮することを求めるものです。費用に相当する金額を上回る報酬を受けることを禁ずる趣旨のものではありません。
ただし、依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはなりません。
なお、宅建業者は、上記に従って、報酬を受ける場合には、媒介契約の締結に際しあらかじめ、その上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。
個人Aから500万円の建物の売却の媒介を受けた事案を例に計算方法を説明します。
【売主A(個人)から媒介の依頼を受けて、500万円の建物売買契約が成立】
1.通常の方法で報酬額を計算する
500万円×3/100+6万円=21万円
2.現地調査費用を上乗せする(ただし、合計して30万円を超えることはない)
(実際の現地調査費用が10万円の場合)
⇒21万円(通常の報酬額)+(現地調査費用分)≦30万円
よって、現地調査費用分として9万円を受領できる。
⇒21万円(通常の報酬額)+9万円(現地調査費用分)+消費税(10%) ≦ 33万円
(実際の現地調査費用が5万円の場合)
⇒21万円(通常の報酬額)+5万円(現地調査費用分)※+消費税(10%) ≦ 33万円
※費用に相当する金額を上回る報酬を受けることを禁じていないので、現地調査費用が5万円であっても、取引の態様や難易度等に応じて媒介業務に要すると見込まれる費用の水準や多寡を考慮して、上限まで受領することもできます。
(2)低廉な空き家等の売買又は交換の代理における特例
宅建業者が低廉な空き家等の売買または交換の代理について、依頼者から受けることのできる報酬の額(代理に係る消費税等相当額を含む)は、前記1により算出した金額の2倍以内となります。
ただし、宅建業者がその売買または交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が前記1により算出した金額の2倍を超えてはなりません。依頼者への説明と合意が必要な点については媒介の場合と同じです。
個人Aから500万円の建物の売却の代理を受けた事案を例に計算方法を説明します。
【売主A(個人)から代理の依頼を受けて、500万円の建物売買契約を成立】
1 通常の方法(媒介)で報酬額を計算する
500万円×3/100 + 6万円 = 21万円
2 現地調査費用を上乗せする(ただし、30万円を超えることはない)
(実際の現地調査費用が10万円の場合)
⇒21万円(通常の報酬額)+(現地調査費用分)≦30万円
よって、現地調査費用分として9万円を受領できる。
代理の場合はこの金額の2倍以内までとなる。
⇒21万円(通常の報酬額)+9万円(現地調査費用分)×2+消費税(10%)≦66万円
(実際の現地調査費用が5万円の場合)
⇒21万円(通常の報酬額)+5万円(現地調査費用分)※×2+消費税(10%)≦66万円
※費用に相当する金額を上回る報酬を受けることを禁じていないので、現地調査費用が5万円であっても、取引の態様や難易度等に応じて媒介業務に要すると見込まれる費用の水準や多寡を考慮して、上限まで受領することもできます。
(3)長期の空家等の貸借の媒介における特例
宅建業者が長期の空き家等の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受ける報酬の額(媒介に係る消費税等相当額を含む)の合計額は、媒介に要する費用を勘案して、その借賃の1か月分の2.2倍に相当する金額を超えない範囲内となります。
○長期の空き家等とは
現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、または将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地・建物をいいます。
たとえば、少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっていたり、相続等により利用されなくなった直後であっても今後、所有者等による利用が見込まれないものであったりする戸建の空き家や分譲マンションの空き室などが考えられます。なお、入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室については、事業の用に供されているものと解されることから、長期の空き家等には該当しません。
ただし、借主である依頼者から受ける報酬の額は、その借賃の1カ月分の1.1倍(居住の用に供する場合は、その媒介の依頼を受けるに当たって借主である依頼者の承諾を得ている場合を除き、0.55倍)に相当する金額以内でなければなりません。
つまり、宅建業者が通常の上限を超えて依頼者から受けることのできる報酬は、長期の空家等の貸主である依頼者から受けるものに限られます。
なお、宅建業者は、上記に基づき報酬を受ける場合には、媒介契約の締結に際しあらかじめ、上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります。
(4)長期の空き家等の貸借の代理における特例
長期の空き家等の貸借の代理については、次の(1)と(2)に掲げる報酬の額((2)にあってはその合計額)は、前記①にかかわらず、その借賃の1カ月分の2.2倍に相当する金額以内です。
依頼者への説明と合意が必要な点については媒介の場合と同じです。