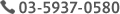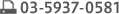公開日 2025年02月22日
こんにちは
最新版「富裕層ピラミッド」で見えてきた、「投資なくしてお金持ちにはなれない」という現実
株価上昇で「いつの間にか富裕層」「スーパーパワーファミリー」が増加
野村総合研究所が、いわゆる「富裕層ピラミッド」の最新版を公表しました。純金融資産保有額別の世帯数と資産規模に関する推計で、発表のたびに話題になるものです。
野村総合研究所のレポートでは、日本の富裕層・超富裕層の世帯数が、2023年に約165万世帯となり、純金融資産総額は約469兆円に達したと推計されています。2021年比で見ると、富裕層・超富裕層の世帯数は11%、資産総額は29%増加したことになります。
特に、株価上昇などの影響による「いつの間にか富裕層」と呼ばれる資産増加層や、都市部居住で世帯年収3000万円以上の「スーパーパワーファミリー」といった新たな層が出現しています。
他方、国民の平均所得額は長期間に渡って減少してきました。
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、2002年の所得額の中央値は485万円でしたが、2023年は405万円となっています。それなのに、日本では富裕層以上が増えているというのです。
これはどういうことなのでしょうか。今回は、日本における資産階層について確認していきたいと思います。
多くの「富裕層」が「超富裕層」にランクアップ?
最初に、野村総合研究所の推計の内容から確認していきましょう。
以下の図をご覧になったことがある方も多いと思いますが、最初に「超富裕層」や「富裕層」といった言葉が具体的に何を指すのか、その定義を確認しておきます。

・純金融資産
預貯金、株式、債券、投資信託、一時払い生命保険や年金保険等、世帯として保有する金融資産の合計額から負債を差し引いたもの
・超富裕層
世帯の純金融資産保有額5億円以上
・富裕層
世帯の純金融資産保有額1億円以上5億円未満
・準富裕層
世帯の純金融資産保有額5000万円以上1億円未満
・アッパーマス層
世帯の純金融資産保有額3000万円以上5000万円未満
・マス層
世帯の純金融資産保有額3000万円未満
考察
超富裕層
株価上昇などの影響によって、富裕層の一部が超富裕層にランクアップしたことが、一世帯当たりの純金融資産の減少につながっていると想定しています。
長期のスパンで見れば、超富裕層は株式市場の上昇などの恩恵を受け、大きく資産を伸ばしました。超富裕層の方が、富裕層よりも増加率は高いのです。
超富裕層はその資産背景を基に、さまざまな金融資産を保有していると想定され、金融市場上昇の恩恵を大きく受けていることになります。また、不動産価格の上昇や相続の影響も考えられます。
いずれにしろ、日本には超富裕層が急激に増加しているということです。
準富裕層も堅調に増加したが…
準富裕層は、足下の一世帯当たりの純金融資産は、富裕層と比べて伸びていません。2005年から2023年でみても一世帯当たりの純金融資産の伸びは限定的です。
準富裕層は、家計負担や住居費の影響によって、資産運用に回せる額が超富裕層や富裕層よりも低く、株価上昇などの影響を彼らほどには受けられていない、ということになるでしょう。
アッパーマス層の減少が意味すること
そして、今回の推計で最も特徴的なデータの1つが、「アッパーマス層(純金融資産3000万~5000万円)」の減少でしょう。
アッパーマス層は、2021年から2023年にかけて 純金融資産が15.1%減少しています。世帯数も726.3万世帯から576.5万世帯と、20.6%の大幅減となりました。
一方で、準富裕層はプラス78.5万世帯、富裕層はプラス14.0万世帯で、合計92.5万世帯が増加しています。
すなわち、この準富裕層・富裕層の世帯増加は、アッパーマス層から上位層へ移行した世帯がかなりの割合で含まれると推測可能なのです。
マス層には大きな変動無し
「マス層(3000万円未満)」は年ごとの変動は少なく、成長率は富裕層などに比べて控えめです。世帯数の増加 3831.5万世帯から4424.7万世帯(プラス15.5%)を鑑みると、資産の増加ペースは緩やかと言ってよいでしょう。
お金持ちほどリスクを取っている
今まで、準富裕層、富裕層や超富裕層が、株価上昇などの恩恵を受けて資産を増やしたり、上位層へ移行したと想定されることを述べてきました。
一方、日本はつい最近まで、資産運用に慎重な姿勢を取る人が多くを占めていました。今回の推計で資産を増やした準富裕層、富裕層や超富裕層の人々は、以前から積極的に資産運用を行ってきたということなのでしょうか?
この疑問の答えを探すのにも、今回の推計は役立ちます。
この20年において最も金融市場が荒れたのは「リーマンショック」でしょう。2009年頃のリーマンショックは、各層にどのような影響を与えているでしょうか? これを確認することで、各層がどの程度積極的に投資をしていたのかを推し量ることができそうです。
<2007年から2009年にかけての純金融資産変動>
超富裕層:65兆円→45兆円(▲30.8%)
富裕層:189兆円→150兆円(▲20.6%)
準富裕層:195兆円→181兆円(▲7.2%)
このように、リーマンショックによる金融市場の影響を強く受けたため、それぞれの資産は減少していますが、超富裕層→準富裕層にかけて影響が小さくなっていることが分かります。
一世帯当たりの純金融資産も確認してみましょう。
<2007年から2009年にかけての一世帯当たり純金融資産変動>
超富裕層:10.7億円→9.0億円(▲15.5%)
富裕層:2.2億円→1.9億円(▲15.9%)
準富裕層:7193万円→6709万円(▲6.7%)※
アッパーマス層:3850万円→3520万円(▲8.6%)※
マス層:1193万円→1195万円(+0.2%)※
※前述のデータでは100万円の単位が四捨五入されているが、ここでは万円単位としている
やはり、リーマンショックの頃から、富裕層や超富裕層は、金融市場の影響を大きく受ける、すなわち資産運用を積極的に行ってきていたことが分かります。
金融市場が大きく崩れた時には影響を受けますが、長期的に見ると資産を大きく増やしていることから、資産運用の戦略は成功していると言えるでしょう。
◇まとめ
日本の各階層の特徴は、富裕層・超富裕層が急成長し、資産が大きく増加しています。そして、準富裕層も安定成長し、資産規模が拡大してきています。
一方で、アッパーマス層の減少が顕著ですが、これには、上位層への移行と下位層への移行が想定されます。アッパーマス層の減少は単純に日本が貧しくなってきていることを示すとは言えないでしょう。
ただ、日本における資産の二極化が進んでいることは間違いありません。特に超富裕層・富裕層の増加が著しく、経済的な格差は拡大している傾向が見られます。
野村総合研究所の推計から学べることは、日本においては資産運用を行ってきたか否かで大きな差が出ているということです。