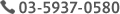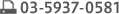公開日 2025年03月01日
こんにちは
「タワマン空室税」の発想が「ピント外れ」と言わざるを得ない理由
投資が物件価格上昇を招いている? 将来的な廃墟化のリスクがある? それぞれの説を検証
1月10日、神戸市の久元喜造市長が、市内のタワマンの空室所有者に対して、新たに課税することを検討していると発表した。
背景にあるのが、2024年5月1日に立ち上げられた「タワーマンションと地域社会との関わりのあり方に関する有識者会議」による提言だ。
2月に提出された最終報告書によれば、2024年2月現在、建築中のものを含めて市内には64棟のタワマンがあり、高層階ほど住民登録のない空室が多く存在するという。
具体的には、40階以上でその割合は33.7%に及ぶ。1階から9階で14.0%、30階以上40階未満で21.2%であるから、上層階に行くほど住民はおらず、また所有者の所得水準が高いと指摘している。
では、なぜタワマンの上層部には住民登録をしない部屋、市外に住む所有者が多いのだろうか? こうした点を踏まえながら、今回は神戸市の「タワマン空室税」について考えてみたい。
タワマン購入者「4つの層」
神戸市の「タワマン空室税」について考える前に、そもそも都市部におけるタワマン購入者はどうなっているのか、というところから整理していこう。具体的には、以下の4つにカテゴライズできる。
購入者層1「地元の富裕層」
1つ目は、地元や周辺の地方都市の富裕層が、「富の象徴」ともいえるタワマンを神戸市で買う、というパターンだ。今はちょっとした地方都市(たとえば県庁所在地)であればタワマンが供給されているが、上層階を購入するのはほとんどがその地域の成功者たちだという。
私がある地方都市で講演を行った後、地元有力者の方々と懇親会をする機会があった。そこでの話題は、もっぱら「その地に建設されるタワマンの最上層階を誰が買うのか」という噂で持ち切りだった。地元商工会のトップ、地元有名企業のオーナーなどといった人たちだ。
ただ、こうした方々はすでに地元に自宅を構えているので、自身が居住する例は稀であり、空室のまま、あるいは会社の迎賓館、福利厚生施設として使用することが多いという。
購入者層2「国内外の投資家」
2つめが、「国内外の投資家」だ。メディアではタワマンを買い漁る外国人投資家のことばかりが取り上げられるが、国内の個人投資家も実は大勢いる。マンション価格の高騰を見込んで、数年後の売却予定で投資する人たちだ。彼らからみれば、タワマンは居住施設というよりも「金融商品」に近い感覚のものだ。
購入者層3「高齢の富裕層」
相続対策として購入し、納税額を圧縮しようというもので、「タワマン節税」などと喧伝されている。
これは、例えば現金で1億円を所有していれば相続時には額面に対して課税されるが、このお金でタワマンを買えば、評価額は6割程度になるため、格好の節税手段になる、というものだ。
昨年、評価手法が見直されるまでは評価額が2割程度になったこともあり、国税庁は時価と評価額の乖離が大きいマンションについては一律で時価の6割にするとしたが、それでも一定の評価圧縮ができ、さらに借入金で購入すれば借入金元本も評価額から控除できるため、タワマン投資をする人が多いのだ。
購入者層4「実需層」
そして4つめが神戸市の期待する「実需層」だ。ただ、最近の建設費の高騰で、こうしたタワマンを購入できる層はパワーカップルなどと呼ばれる、夫婦共働きで世帯年収が1500万円程度になるごく一部の層であり、こうした人たちが多額の住宅ローンを組んで買っているのが実態である。
今回の提言を検証してみる
さて、タワマンの所有者層がこうした人たちであることを理解したうえで、今回の提言を眺めてみよう。
まず「投資で買っている人が多いので、価格が高止まりしている」という問題について。
そもそも不動産投資を行う投資家にも2つのタイプがある。「賃貸資産として中長期で運用する人」と、「短期で売却益を取ろうという人」だ。
前者は賃貸としての利回りを重視する。したがって期待利回りを実現できなければ投資は失敗である。賃借人がマンションを住居(あるいは事務所)として利用するのだから、価格水準も当然期待利回りを実現するレベル(例えば年3%や4%程度)に収斂していくものであり、次第に調整されていく。行政があれこれ言う必要はないだろう。
おそらく後者(売却益狙い)が問題だと言うのだろうが、投資は値上がりもあれば値下がりもある。
現在はたまたま値上がりの時期が長く続いているので投資家もアグレッシブだが、マーケットが変わる、つまり相場が下がり始めると、投資家は一斉に売り始める。
みんなが一斉に売りに出すと価格の下げ足は速く、底値買いする人が少なければ、価格はやがて実需層の手が届く範囲に収まる。有識者の皆様は、投資は儲かるから価格が上がるという一面的な側面だけを見ているようにみえる。やや的外れな議論である。
将来的な「廃墟化」のリスクは
次に、住民構成がバラバラであるから、管理組合での意思統一が難しく、管理費や修繕積立金の未払いが発生し、最悪の場合、将来廃墟化するリスクが高い、という指摘について。
これはかなり的外れだ。投資家にとって、自身の投資資産であるタワマンの価値が下がっては投資にならない。必要な管理や修繕を施すことは、資産価値を維持するためには絶対条件になる。
この問題はタワマンよりも、築古で所有者や住民が高齢化しているマンションで大問題となる。
年金暮らしで経済的余裕のない高齢者が、管理組合の要請に従わずに「自分はもうすぐ死ぬからそんな修繕は必要ない、ましてや建替えなんてまっぴらだ」と総会が紛糾するのは築古マンションの常だ。
また、「空室所有者はゴミ出し、消防、防災、防犯などのサービスに協力していない」という理由もよくわからない。
タワマン内でのゴミ出しは住民が少ない分、ゴミの量は少ない。戸建て住宅であれば、防犯や防災における行政サービスを地域全体で満遍なく施す必要があるので、空き家部分にまでサービスを施すのは無駄であるということはわかるが、タワマンは一棟が対象となるので、行政サービスが無駄になるとは理解しにくい。
「空き部屋」をどう判断するのか
課税対象とする空室の定義や調査方法もあきらかではない。
賃貸資産でたまたまテナントが入っていない場合はどう判定するのか。セカンドハウスとして神戸の街を楽しんでいる人に課税するのか。居住用資産であるのに、長期の海外出張や一時的な転勤などで家を空けている場合はどうなるのか。いずれも定義がはっきりしない。
調査はどうするのか。水道メーターをチェックするなどが考えられるが、上記の状態であるかどうかなど細かなチェックができるはずがない。
また久元市長は、晴海フラッグの例を挙げて警鐘を鳴らしているが、これも的外れだ。
晴海フラッグは元都有地。通常、公用地等を民間に住宅用として卸す際には、一定期間の転売禁止や法人による住戸の購入を禁ずるなどの制約を施すのだが、なぜか晴海フラッグでは行われず、販売がヒートアップしたとされる。
PHOTO:Ryuji/PIXTA
ところが今回の報告では、かつて民間が分譲した既存のタワマン所有者に対して課税するというものだ。これはどうみても後出しじゃんけんである。
タワマンが多数建設されたため、小学校などがキャパオーバーになって対応できないなどの発言もあるが、空室所有者に課税するのではなく、今後タワマンを建設しようとする業者から開発協力金を徴収すればよい。実際に東京江東区などでの実施例がある。
実はすでに神戸市は2020年7月にタワマン規制を行っている。JR「三ノ宮」駅周辺を「都市機能誘導地区」として約22.6ヘクタールの地域に対して住居施設の建設を禁じ、オフィスや商業施設の誘導を行うものとしている。
また「新神戸」駅からJR「神戸」駅周辺一帯の敷地(敷地面積1000㎡以上)の容積率を400%とし、事実上タワマンは建設できないように規制している。
こうした施策は、神戸市の自治体としての都市計画の一環であるので、一つの考え方として理解できるが、既存タワマンの、しかもまったく曖昧な定義のもとで空室税を課税することには疑問しか感じえない。
また徴収した税金をマンション管理行政(マンション管理アドバイザーの派遣や広報)やオフィスビルに対する助成に使うとする使途についても明確ではない。
◇
空室かどうかを無理やり判定するくらいならば、諸外国でも多くの事例があるように、非居住の外国人所有者に対して、固定資産税を多く徴収するほうが得策だろう。外国人所有者を一方的に排除するという意味ではなく、外資マネーまで参加した投資ゲームに関しては一定の課税を行うということだ。
神戸市のタワマン空室課税、ぜひ再考を促したい。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード