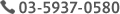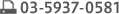公開日 2025年03月15日
こんにちは
不動産「買い放題」で外国人が無双しているようです。そこで
外国人の不動産購入、そもそも何が問題なのか?
今回は専門家の解説をもとに、外国人の土地取得の問題点や規制が難しい背景を整理していく。国土の買収という事態に日本はどのように向き合うべきかを、改めて考えてみたいです。
外国人に買われることの「3つの問題点」
売られゆく日本に危機が迫っている―。
日本の土地が外国人に買われることに対し、SNSなどで「静かな侵略だ」として警鐘を鳴らす声は少なくない。
しかし外国人に土地を買われることの何が問題なのか、実はよく分かっていないという人も中にはいるのではないだろうか。まずは、そもそもの問題点を整理することから始めよう。
専門家によるとまず3つの問題点があげられる
(1)国家の財源としての税金が取れなくなる
1つ目の問題は、もし固定資産税などを滞納された場合、所有者が外国人だと税を取るのに大きなコストがかかることだ。言語の問題、連絡手段の有無など、自治体の対応には限度がある。関連して、所有者不明の土地が増えてしまうことも問題点だという。海外での外国人から外国人への転売は実態上、報告不要になっており、税務担当の職員(徴税吏員)の権限は国外に及ばない。たとえば大阪市では海外向けの税金の督促状が2018年から2020年にかけて、1900件から3272件へと1.7倍に増えたという。その後の処理については公表されていないが、大阪市としては徴税を諦めるしかなくなるだろう。
(2)安全保障上の懸念
2つ目は、安全保障に関する問題だ。現在は、防衛関係など日本にとって重要な役割を担う施設の近くであっても、外国人は土地の所有を規制されない。常識的に考えて問題がある横須賀基地での事例(2024年5月9日防衛省発表)のように、平時でも重要施設の近くからドローンを飛ばすことができ、有事の際には施設を即座に壊滅させてしまう、といったことも可能性として考えられるという。2022年に施行された「重要土地等調査法」では、重要施設の1キロメートル圏内の土地利用状況を調査できるようになった。しかし直接の土地売買規制にまでは踏み込めていないのが現状だ。
(3)国家の発展の芽を摘んでしまう
最後に、国家の発展を妨げる点も問題だという。
国家が何をやるにしても国土がなければ始められません。再エネ用地や港湾、物流拠点、水源林、農地など、現行の『重要土地等調査法』の対象外になっている土地も重要国土です。それらの土地を海外に押さえられることの是非は考える必要がある。
たとえば道路の新設や災害時の復旧事業、不法投棄された産業廃棄物の撤去など、すべての公共事業は地権者の了解がなければ行えない。
将来、意図的にそういった事業を妨害することも可能になるのが問題です。外資を一括りにせず、『世界が認める法治国家』と『それ以外の国家』を分けて考えるべきである。
なぜ規制が実現できないのか?
全面的にしろ部分的にしろ、専門家も「規制が必要ではないか」と訴える外国人の不動産取得問題。
では、今すぐにでも規制してしまえば良いのではないだろうか。そう考える人もいるかもしれないが、今の日本で規制が実現できていない背景にはさまざまな要因が絡んでいる。
外国人の土地取引を規制するのが難しい理由として、法的な観点では大きく以下が関わってくる。
1.GATSにおける国際ルール
日本が1994年に加盟したWTOのGATS(サービス貿易に関する一般協定)では「内国民待遇の保障」という国際ルールがあり、土地取引で外国人にだけ特別な規制を設けることはできないとされている。
たとえ外国人の土地取得を規制する法律を作っても、GATSに違反しているということから他のWTO加盟国に提訴される可能性がある。
内国民待遇の保障とは、外国のサービスや事業者に対して、自国のものと同じ扱いをしなければならないという原則だ。
土地取引の例でいえば、外国人が日本の土地を購入する際は、日本人が土地を購入するときと同じ条件で取引できるようにしなければならない。
このルールは、GATSの締結時に各国があらかじめ約束した分野でのみ適用される。土地取引の分野についてはルールを「留保」し、適用されないようにした国も存在する。しかし、GATS加盟当時の日本には外国人土地法(後述)を除いては外国人の不動産取得に規制法がなく、また外資を呼び込みたいという思惑もあったことから、この留保をつけなかった。
この点に関して、「今のように、外資によって多くの国土が買われる事態は想定外だったのではないか」という意見もある。
当時は国家安全保障局も存在せず、安全保障の観点で総合的に判断を下すような部門がなかったことも一因と考えられるという。
ただ、この国際法にも「安全保障例外」という考え方がある。重要な国益保護のためであれば、通常の国際法上の制約を免れるというものだ。正当な根拠があれば、安全保障例外として後から土地取引についての規制を設けることは可能になる。
「たとえば、日本と同じようにGATS加盟時に留保をつけなかったシンガポールもインドも現在は外国人の土地売買を規制しています。イギリスやフランスもそうです。要は、安全保障例外をどう解釈するかという話です」
2.日本国憲法第29条の財産権
日本では、憲法によって日本人・外国人問わず財産権(自分の財産を自由に使ったり、処分したりできる権利)が保障されている。土地等の取引を制限することは、この財産権の侵害につながると考えられる。
明治憲法では所有権(=財産権)について第27条に規定があり、「日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルゝコトナシ」と、権利の主体が日本人に限定されていた。
しかし、戦後の日本国憲法第29条では「財産権は、これを侵してはならない」とされ、主体の記載がない。当事者が外国人でも差別なく財産権が保障されるということだ。
国籍によって土地取引を制限する差別的な取り扱いは、外国人の財産権の侵害に繋がる。また日本人の所有財産である土地を外国人に売却できないよう規制することは、日本人にとっての財産権侵害にもなってしまう。こうした憲法上の規定が、外国人の土地取得を制限することが難しい要因となっている。
またこれらに加えて、「国際法の相互主義」も、外国人の土地取引の規制が難しい要因として挙げられることがある。国同士の関係は対等であり、お互いに対して同じ待遇を与えるという考え方だ。
日本が他国に対して自国の土地の所有を禁じた場合、相手国側もまた日本に対して自国の土地の所有を禁止することができる。