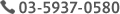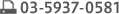公開日 2025年03月16日
こんにちは
不動産「買い放題」で外国人が無双しているようです。そこで
外国人の不動産購入の問題点と対策 続きです
☆「外国人による不動産購入について、全面的な規制には賛成できないという意見もある
日本では基本的人権として経済活動の自由が保障されていること、外国人にもその権利が平等に認められることから、外国人の不動産取引を「原則制限すべきではない」と考えているという。しかしそのうえで、「全面的ではなく、部分的にはやはり規制を設けるべきだと考えます」と語る。土地だけではなく建物の取引も含め、現状の制度では問題があると考えているそうだ。居住用ではなく単なる投資として物件を購入し、売り抜けていく外国人も多いと聞きます。連絡が取りづらい海外で転々と譲渡が繰り返されれば、所有者不明や管理不全の不動産が増加する一因になることも考えらる、というのだ
このように日本では、さまざまな要因から外国人の不動産取得を規制することが難しい状況となっている。
しかしながら
☆中国人は「相続税ゼロ」…不公平な競争
さらに、中国には相続税が存在しない。所有者の代替わりのたびに相続税を払わなければならない日本人と、相続税ゼロの中国人とでは、公正な競争ができませんよね。これも国内外の逆差別が起きている。相続税がなければ購入した土地をいくらため込んでも問題なく、中国人に買われた土地は二度と日本に返ってこない可能性も考えられるという。
外国人の不動産保有に関して、追加税など新たな税制度を整えるなどの対応も必要だ。
☆それでは今後、どのような方策が必要になるのだろうか。
「ただ1つの有効な手立てというものはなく、総合的な策が必要」
「まず今ある登記情報だけでは不十分です。登記簿や住民基本台帳等に連動させた土地情報の基盤整備が必要でしょう。所有者を即座に把握できる近代的な名寄せシステムが不可欠です。また今は、外国人や外国法人がダミーの日本法人を立てたり、ペーパーカンパニーの合同会社と匿名組合を組み合わせて不動産を購入しているため、所有者を特定できないケースが多々あります。実質的な土地の支配者が秘匿されない仕組みづくりも求められます」
☆それでは日本以外の国の場合は、外国人による不動産取得に対してどのような取り組みをしているのだろうか?
東南アジアを拠点に海外不動産取引のコンサルティング・管理を行うProperty Access株式会社の代表、風戸氏は「そもそも日本のように外国人が無条件に不動産を持てる国というのはかなりレアです」と語る。
たとえば中国は外国人に対しての規制が非常に強く、外国人による不動産の所有権取得は認められていない。
韓国では外国人による不動産取得は基本的に可能だが、事前申告が義務付けられており、軍用地や島嶼(とうしょ)部、農地などについては特別な許可が必要となる。
ほかにも外国人が購入できる不動産の価格範囲を限定しているマレーシア、外国人の中古物件の購入を制限し原則として新築物件の購入のみ認めるオーストラリアなど、各国ではさまざまな形の規制が存在する。
税金による規制を設けている国もあり、基本的に外国人の場合は国民よりも税金が高くなるような仕組みであることが多いという。たとえばシンガポールの場合、外国人が居住用不動産を購入すると物件価格の60%の追加印紙税が生じる。
日本ではこうした規制がなく、外国人も無条件で不動産の所有権を得ることができる。他国と比べても不動産を買いやすいことから、注目を集めやすい。
「他国より融資が簡単な側面もあり、不動産価格も世界的に見てまだ安い。言葉の壁さえなんとかできれば、日本は外国人にとって不動産投資向きの最高の国だと思われるのではないでしょうか」(風戸氏)
こうした背景からも、現状の日本における不動産取引の特異性が浮かび上がってくる。
☆外国人の土地取引の可否については、明治時代からさまざまな法律が制定・廃止されてきた。
特に近年は本件の問題意識が高まり、2023年以降は3回にわたって関連法案が提出されているが、いずれも成立には至っていない。
直近の2024年12月に衆議院へ提出された「外国人土地取得規制法案」は、2021年成立の「重要土地等調査法」をさらに強化し、より包括的な規制を目指す目的で作成された。
法案の作成・提出に携わった国民民主党の政務調査会長、浜口誠議員は「国土は国民の生活や経済活動の基盤となるため、取得、管理、利用の面でしっかりと対応していく必要があります」と語る。また現行の法律では、外国人の土地購入を規制することはできず、あくまで調査が可能という範囲にとどまっている。浜口議員は「日本の土地である以上、外国人による取得や利用を一定程度規制することはやむを得ない」として、規制に向けて今後も動いていきたいと語る。
規制の実現にあたっては、やはりGATS協定の「内国民待遇の保障」との整合性などさまざまなハードルがある。しかし「決して簡単なことではないが実現不可能ではない」と熱意を見せた。
「近年、安全保障の意識が高まっているからこそ、2020年に結んだRCEPでは外国人の土地取引を制限できるという留保がつけられたのです。もう一段階踏み込んだ問題意識を政府と共有しながら、規制の具体的なアクションにつながるような働きかけをしていきたいと考えています」(浜口議員)