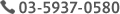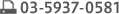公開日 2025年03月30日
こんにちは
田園都市線沿線に広がる郊外住宅地の「勝ち組」?東急が「多摩田園都市」にかけた執念
カギは「鉄道」、多摩田園都市開発の歴史を紐解く
たまプラーザ駅は、多摩田園都市の核として整備された
昭和の時代、戦前期から戦後の戦災復興期、高度経済成長期、バブル期を通じて主に住宅地が盛んに開発され、それに伴って東京の地価は右肩上がりで高騰した。そのため、戦後間もない頃からデベロッパーは「郊外」に着目した。
東京で郊外開発を積極的に進めた事業者は多々あるが、なかでも東急電鉄は鉄道とのシナジー効果を最大限に発揮したデベロッパーでもある。本稿では東急が開発した住宅地、「多摩田園都市」を取り上げる。
東急田園都市線の沿線を中心に広がる多摩田園都市は、もとより住宅地として成功が約束されている場所ではなかった。過去には、近隣エリアで小田急電鉄が大規模開発を行ったものの、思うように計画が進まなかった経緯もある。
そこからどのようにして、5000ヘクタールにもおよぶ住宅地ができあがったのか。昭和30年代から始まる開発の軌跡をおさらいすると、東急がまちづくりに燃やした執念が見えてきた。
◇
中心地「たまプラーザ駅」命名のナゾ
多摩田園都市で東急総帥としての手腕を発揮したのがたまプラーザ駅(横浜市)だ。
たまプラーザ駅が所在する場所は元石川という地名で、「たま」は言うまでもなく多摩を意味し、「プラーザ」はスペイン語で「広場」を意味するplazaに由来する。
奇抜なネーミングだが、たまプラーザの名称は昇が考案した。そうした経緯からも、同エリアの開発に意気込みを感じさせるが、この駅名になったことで東急は駅周辺開発に情熱を注ぎ込み、駅前には東急系列の商業施設が立ち並んでいった。
たまプラーザの駅前から少し歩くと住宅地へと風景は移り、ここには第2の田園調布と呼ばれる高級住宅街が形成されていった。
たまプラーザの駅前に田園調布のような整然とした街路は整備されていないが、住宅地にはクルドサックが整備されるなどの特徴的な街並みになっている。
クルドサックは東武鉄道が戦前期に高級住宅街として整備した常盤台(東京都板橋区)に見られる袋路で、そのほかにもラドバーン方式と呼ばれる歩車分離も導入された。
道路・街路にこだわったあたりに、多摩田園都市がマイカーを前提とした五島の思想を読み取ることができる。
複数路線と接続し、人口増加に拍車
たまプラーザ駅は多摩田園都市の中心と位置づけられたが、自動車交通を軸に計画された背景から鉄道的な特徴は乏しかった。それでも1993年には、横浜市営地下鉄ブルーラインが、隣駅であるあざみ野駅(横浜市)まで延伸。
ブルーラインは横浜駅と桜木町・関内という横浜の中心地を結ぶほか、新横浜駅、さらには港北ニュータウンを貫く路線にもなっているので多くの需要を見込める。
ブルーラインと田園都市線が接続したことで、多摩田園都市全体の交通利便性は格段に向上。ますます沿線人口の増加に拍車がかかり、田園都市線の利用者も増加した。そのことから、2002年にあざみ野駅は急行停車駅へと格上げされる。
ところで、現在は渋谷駅―中央林間駅の区間全てが「田園都市線」として運行されているが、以前は渋谷駅―二子玉川駅間が「新玉川線」、それ以外が「田園都市線」という2つの路線になっていた。2000年に路線名が改称され、両者が「田園都市線」に統一されることとなる。
2つの路線に分かれていた頃も、特に乗り換えが発生していたわけではない。利用者も気にする必要はなかったが、改称前年の1999年には田園都市線区間の最高時速が110キロメートル、新玉川線区間が90キロメートルへと引き上げられて、所要時間が短縮。
これが多摩田園都市の通勤圏拡大になることから、人口流入を促した。
最高時速の引き上げや田園都市線への統一は、長津田駅で接続する「こどもの国線」にも影響を及ぼした。「こどもの国」は旧陸軍用地だった場所で、戦後は米軍に接収されていたが1965年に児童厚生施設へと生まれ変わっている。
東急グループが一丸となって多摩田園都市に心血を注いだ成果もあり、エリア人口は開発当初の約1万5000人から開発50周年を迎えた2003年には56万人に達した。
2011年には開発総面積が5000ヘクタールにもおよぶ広大な多摩田園都市の開発計画が完了した。計画完了後に人口増は鈍化したものの、その後も人口は増え続けて2013年に60万人を突破している。
押し寄せる高齢化の波
東急が開発に取り組んだ多摩田園都市の発展は平成後期まで続いたが、他方で、地方都市は平成期から人口減という社会問題に苦しんでいる。
多摩田園都市は東京・横浜のベッドタウンという要因に支えられて、郊外というハンデを負いながらも人口減による大きな衰退は見られない。
それでも開発が盛んだった頃に住み始めた世代が高齢化し、2000年頃から顕著になっている都心回帰の影響を受けて若年世帯の流入が滞っている。
住民の高齢化は街の新陳代謝を鈍らせ、活気を奪っていく。
多摩田園都市には各駅からバスが頻繁に運行され、駅から離れていても交通の利便性は高いエリアだった。しかし、丘陵地という地形的な特性も相まって、バス停から自宅までの距離は短くても高齢者にとって身体的・精神的な負担が強い。
東急は多摩田園都市で新たに浮上している高齢者の移動困難という課題を解消するべく、虹が丘(川崎市)やすすき野(横浜市)といったエリアで、自動運転のバスの実証実験を始めた。
将来的に自動運転バスを多摩田園都市全体に広げることで、持続可能な住宅地を目指そうとしている。虹が丘・すすき野での取り組みは、その第一歩に過ぎない。
◇