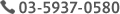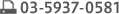公開日 2025年04月13日
こんにちは
朝の過ごし方は人によってさまざまです。朝からしっかり食べて精力的に動いている人もいれば、朝食を抜いてあわただしく出かける人、ぼんやりと過ごす人。だが、朝の時間の使い方次第で、生活の質も、病気の発症リスクも変わる可能性がございます。
本特集では時間栄養学に基づき、朝から健康的でアクティブな1日を送るための「最適な朝習慣」を解説。それに欠かせない「朝食や運動」についても詳しく言及していきます。初回は、体の不調に直結する体内時計のメカニズムを解説します。
「何をどのくらい」食べるかより、「いつ」食べるかが大事
「朝昼晩、健康的な食事をしっかり3食とる」。この「3食」のうち、一番ハードルが高いのは朝食ではないか。忙しくて朝食をつくることができなかったり、食べるのを忘れたりすることがよくあるからだ。加えて朝食は、昼食や夕食と比べ、「いつ」「何を」「どのくらい」食べればいいか、分かりにくい面がある。例えば、「バナナ1本で済ませている」「パンと目玉焼きが定番」という人は、それでいいのだろうか。
何よりもまず、『朝起きたら食べる』という習慣を持つことが大切です」
なぜ朝食を重視すべきなのか。その背景には、人間が生まれながらに持つ、「体内時計」が関わっている。私たちの体は、1日24時間ではなく、「少し長め」のサイクルで動いている。そのため、生活リズムを日々リセットして24時間に合わせなければ、体内時計が乱れ、体調を崩しやすくなる。さらに、体内時計が乱れている人は、肥満になりやすく、糖尿病や高血圧といった生活習慣病のリスクも高くなる。
では、朝食と体内時計にどんな関係があるのか。体内時計のリセット効果をさらに高めるには、どんな朝食がいいのか。今回は朝食に関するこれらの疑問を解消し、朝からギアを上げて過ごすためのポイントを見ていこう。
朝食が体内時計を動かし、心身を活動モードに切り替える
朝食によって期待できる主な効果
- 体温が上がる
- 代謝が上がる
- 1日を通して血糖値を上がりにくくする
- 交感神経のスイッチを入れ、心身を活動モードに切り替える
- 「夜型」の生活リズムになるのを防ぐ
朝食をとった後、変化を実感しやすいのは「体温」だろう。皆さんも、食事をとると体が少し温まった、という経験はないだろうか。これは「食事誘発性体熱産生」という仕組みによるものだ。食べること自体に体温を上げる作用があり、夕食よりも朝食のほうが体温上昇の効果が高いことが分かっている。
朝食には、肝臓をはじめとする全身の「末梢時計」を動かす作用もある。肝臓は体内の物質を分解・合成する「代謝」の機能を担う臓器だ。この肝臓は、朝食によって代謝が上がり、エネルギーを消費しやすくなる。「朝食を抜くと太る」と言われるのはこのためで、太りにくい体をつくる意味でも朝食は重要だ。
さらに、朝食は「自律神経」との関わりも深い。自律神経とは、呼吸や消化、血圧など、生命を維持するために必須の機能をつかさどるシステムのこと。そして自律神経の1つである「副交感神経」は、寝ている間に優位になり、心身ともにリラックス状態となるが、そこで朝一番、「活動するぞ」というスイッチを入れるのが朝食だ。起床して朝食をとると「交感神経」が優位になり、心身がアクティブな状態になる。
「だから朝食をきちんととる人は、午前中からパフォーマンスが上がりやすくなります。一方、朝食を抜くと副交感神経が優位なままなので、午前中はパフォーマンスが低く、頭がぼーっとして仕事がはかどりにくいのです。朝食を抜いた状態が続くと、他にも悪い影響が出てくるので、朝食はきちんととりましょう」