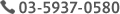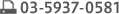公開日 2025年06月11日
こんにちは
法人の登記を書き換えて「勝手に物件売却」、防ぎようがない「乗っ取り型」地面師の犯行とは
司法書士も「見抜けない」、14億円だまし取られた大阪の不動産詐欺
報道によると大阪の繁華街・ミナミで昨年2~3月ごろ、法人の新代表になりすまして不動産の売買契約を結び、買主から14億円余りをだまし取った疑いで、会社役員の男らが今年6月に逮捕された。
法人の不動産オーナーや物件購入を検討する全ての投資家は、こうした事件の被害者になり得る。
専門家は「このようなケースは売買契約の現場でも見破るのがかなり難しい」と語るが、具体的にどのような手口だったのか。被害に遭わないために、投資家にできることはあるのだろうか?
法律に詳しい弁護士や売買現場をよく知る司法書士に、「法人乗っ取り」による不動産売買詐欺について解説してもらった。
「法人乗っ取り」の手口
報道によると、大阪・ミナミの事件で犯行グループは下記の手口を取ったとみられている。

・本来の不動産所有者(法人代表者)名の借用書を偽造
・偽造借用書を役所に提示し、代表者の住民票の写しを取得(住民票は債権回収や訴訟といった正当な理由があれば、本人以外の第三者も取得可能)
・住民票をもとに運転免許証を偽造
・偽造免許証を用いて、役所で代表者の印鑑登録を別の実印に変更
・変更登録済みの実印を用いて、役所で法人の登記変更。容疑者の1人を新代表として申請
・容疑者が法人の新代表を名乗り、買い手に不動産売却を持ちかける
・買い手が購入代金として14億円超を支払う
つまり、売買契約の現場で本来の法人代表者になりすますのではなく、代表者が交代したという体で法人そのものを乗っ取った形だ。
報道によれば容疑者は本来の所有者の甥を装い、土地と建物を売却する理由について、「叔母ともめている」などと買い手に説明したという。
不動産投資家の「資産管理法人」も狙われる?
今回のケースでは、法人登記が不正に書き換えられ、乗っ取った代表者によって不動産売却手続きが行われた。
乗っ取りが行われた法人の登記(2025年6月13日時点)
不動産関係のトラブルに詳しい関口郷思弁護士は「このような代表者の書き換えは意外と簡単にできてしまう」と語る。
「不動産取引に関わらず、法人の代表者が不正に書き換えられるということは以前からありました。会社の支配権争いで一方が無理やり自分を代表者として登記するケースや、会社を乗っ取り代表者として会社の預金を下ろして持ち逃げするケースなどがあります」
このような手口が用いられる場合、本来の代表者の「解任」の登記をした後に、新しい代表者を就任させることが多いという。
代表者が自らの意思で「辞任」する場合は、辞任届のほか原則として印鑑証明が必要になるが、「解任」の場合は株主総会で解任を決議したという議事録だけで足り、偽造などの手間が少なくて済むためだ。
登記を管理する法務局も、明らかに不正な登記申請だと思われる場合は却下するが、そうでない場合は登記できてしまうのが現状だという。
こうした手口のターゲットとされる法人に条件はなく、どんな法人も対象になりうる。不動産投資家のいわゆる「資産管理法人」も例外ではない。
その一方、こうした乗っ取りを事前に防ぐことは「ほぼ不可能」だという。
「役員が全員解任されたときに限り、登記完了後に法務局から通知が行くようになっていますが、取締役の一部が解任された場合や、辞任の場合は通知が行くことはありません。登記自体は通ってしまうため、事前には対策のしようがないというのが現状です」(関口弁護士)
取締役の解任に関しては、会社法上、本人が拒否したとしても株主総会で強制的に行うことができるようになっている。解任の登記に際しても、本人の同意や手続きへの同席などは必要ない。
問題を起こした取締役を解任して速やかに登記を変更させることができる仕組みを担保するため、この部分は変えようがないが、そこを悪用されやすくなってしまっているという、板挟みの状況だ。
一方、このような法人乗っ取りにより不動産が勝手に売却された場合、売買は無効なので不動産は戻ってくるものの、法人が買主に代金の返還をしなければならないケースもあるという。
それが、売買代金が現金支払いなどではなく、法人口座に一度振り込まれてから持ち逃げされたケースだ。法人口座に振り込まれた代金は、すでに乗っ取り犯が持ち逃げをしていたとしても、代金はその口座の持ち主である法人が受け取ったことになるので法人が返還しなければならない。
司法書士には「どうしようもない」
司法書士法人さえき事務所の代表、佐伯知哉司法書士は、「この手口でやられるとどうしようもない」と話す。
そもそも不動産の売買において、司法書士は以下のような形で「登記」に関わることになる。
(1)買主と売主で売買契約書の取り交わし
(2)売主・買主の本人確認と登記申請の意思確認(司法書士)
(3)登記に必要な書類一式を確認(司法書士)
(4)買主が売主へ代金を支払う
(5)売主への代金着金後、当日中に法務局へ登記を申請(司法書士)
→登記申請が法務局に受理され書類に不備なく手続きが完了すると、買主は確定的な所有権を得る(第三者対抗要件の具備)
個人の売主による詐欺の場合、別人が本来の不動産所有者のフリをするため、身分証明書などの本人確認でなりすましを見破ることも可能になる。
一方、売主が法人であり、代表者が交代したという体で登記を書き換えられているといったケースでは、所有者そのものが別人にすり替わってしまう。
まとめ:
売買の現場に参加している売主が「登記簿上の所有者」であるため、一見違和感なく見えてしまう。登記の事実を前提に本人確認が行われる以上、司法書士としても違和感に気づくのは難しい。
「偽造した免許証によって印鑑登録と法人登記の変更がすでに行われ、『法人の代表が交代した』ことを証明する書類が発行されてしまっている。その書類自体は本物なので、疑いようがありません」
佐伯氏によると、過去にこうした「法人の乗っ取り」による大きな地面師事件はほとんどなかったものの「この方法でやられると厄介だ、ということは以前から危惧していました」と語る。
「法人の登記は変更がしやすいのが現状なので、今後また同じようなことをやられたらどうするのか、というのは頭の痛い問題です」