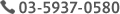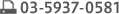公開日 2024年08月04日
日銀が追加利上げを決めたことを受けて、大手銀行は、普通預金の金利を今の5倍に引き上げると相次いで発表しました。各行とも、普通預金の金利の引き上げは、ことし3月のマイナス金利解除以来です。
一般論としての「金利上昇」と「不動産価格」の関係
金利が上昇すると、不動産価格にはどのような影響があるでしょうか?
一般的に、「金利が上昇すれば不動産価格は下がる」とされています。感覚的には、「金利が上昇すれば景気が冷え込み、高い家賃が取れなくなるかもしれない」、もしくは「借入金利が高くなるので、不動産を買う人が減少するのではないか」ということが、その理由として挙げられるでしょう。
このような普通の感覚をきちんと理論付けるために、不動産の世界では、「収益還元法」という考え方が用いられています。収益還元法は、将来的に生み出されるであろう利益をベースにして、不動産価格を求める評価方法です。
収益還元法では、対象不動産の収益対比で「投資家がどの程度の利回りを求めるか?」という観点で評価します。投資家が求める利回りなので、借入金利が上昇すれば、金利を払う分だけ投資家が期待する不動産の利回りは高くなるでしょうし、テナントの家賃が低下するリスクがあるのであれば、そのリスクを織り込んで、やはり高い利回りを投資家は求めるでしょう。
そのようなわけで、収益還元法では、不動産価格を以下の計算式で算出します。
不動産価格=年間の利益(家賃収入-経費)÷還元利回り(キャップレート)
この計算式のポイントは、計算式の分子に影響を与える「経費」には、借入金の支払利息も含まれるということです。
すなわち、金利が上昇し、それに伴って借入金利も上昇すると経費が増え、1年間の利益が減少します。それに伴って、不動産価格が下落するということが分かります。これが、金利上昇に伴って不動産価格が下落すると言われる要因の1つです。
加えて、不動産価格の計算式における「還元利回り」も金利の影響を受けます。
通常「還元利回り」は、経済動向や周辺の不動産市場(対象とする不動産がオフィスならばオフィス市場、賃貸住宅ならば賃貸住宅市場)の状況、対象不動産の市場における競争力などから設定されます。言い換えると還元利回りは、「この不動産は何%の利回りで買いたい人がいるのか」という観点で、周辺の取引事例や、現在売り出されている他の収益物件の利回りを基にして計算されるということになります。還元利回りは、以下のような計算式で求められます。
還元利回り=長期国債金利(リスクフリーレート)+リスクプレミアム
※リスクフリーレートは、リスクがほとんどない金融商品(預貯金や国債など)から得られる利回りのこと。リスクプレミアムは、リスク資産(株式や不動産など)の期待収益率とリスクフリーレートの差のことを指す
不動産投資が長期国債金利、すなわちリスクフリーレートと同じ利回りしか確保できないとなれば、誰も投資は行いません。長期国債金利にリスクプレミアムという上乗せがあって初めて、投資家にとって不動産は投資対象になるのです。
そしてこの還元利回りは、計算式が指し示しているように長期国債金利に連動していることが分かります。ここで、もう1度、不動産価格を求める式を確認しましょう。
不動産価格=年間の利益(家賃収入-経費)÷還元利回り(キャップレート)
先ほど、金利が上昇した際には経費の増加を通じて、分子である1年間の利益が減少すると説明しました。
そして、前述のように、金利が上昇すると還元利回りも上昇することになります。還元利回りが上昇するということは分母が大きくなるということですので、不動産価格は下落することになります。
まとめると、
「金利が上昇すると1年間の利益も減り、還元利回りも上昇するので、計算式における分子と分母、ともに金利上昇の影響を受ける」ということが分かります。このように、金利上昇が起きると、「机上の計算では」不動産価格が下落することになるのです。
中古不動産を購入する際には、金利の動向を注視し、適切なタイミングで購入することが重要です。今のような金利上昇局面では、価格が下がる可能性があるため、お得に購入できるチャンスかもしれません。
城東不動産販売株式会社
~住まいに対する想いを一緒に。~
〒169-0074
東京都新宿区北新宿2-18-10
TEL:03-5937-0580(代表)
FAX:03-5937-0581
Mail:info@0359370391.com